モバイルバッテリーの安全性と、MOTTERUの想い ―― 誰もが持ちたくなるようなプロダクトを、安心とともに ――

INDEX
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、タブレット、電子書籍端末――。
私たちの生活を支えるデジタルデバイスの多くが、リチウムイオン2次電池で動いています。外出先や仕事の移動中でもそれらを快適に使うために欠かせないのがモバイルバッテリーです。
いまや、モバイルバッテリーは現代人の生活における“なくてはならない存在”になりました。
しかしその一方で、発火や膨張などのトラブル、あるいは誤った廃棄による火災事故など、安全性に関する課題が年々顕在化しています。
便利で身近な製品だからこそ、その扱い方や仕組みを誤解してしまうこともあります。こうした現実に対して、私たちMOTTERUは深い危機感と使命感を持って取り組んでいます。
「誰もが持ちたくなるようなプロダクトの開発」。それは単にデザインや性能を追求することではなく、
“持っていて安心できる”“信頼して使える”という根本的な価値を大切にすること。
MOTTERUが目指す「持ちたくなる」とは、心地よさと信頼、そして安全の調和なのです。
◆ 安全に使うために知ってほしいこと
◆ 安全性の証 ― PSEマークについて
◆ 近年の出火・火災件数など具体的数値データ
◆ MOTTERUの安全への取り組み
◆ 情報発信による啓発活動
◆ 「誰もが持ちたくなるプロダクト」を、安全とともに
◆ 最後に:少しでも事故を防ぐために
________________________________________
◆ 安全に使うために知ってほしいこと

モバイルバッテリーには、軽量で高エネルギー密度を誇る「リチウムイオン電池」や「リチウムポリマー電池」が使われています。
リチウムポリマー電池は、形状の自由度が高く薄型化しやすいのが特徴で、スマートなデザインの製品に多く採用されています。
いずれも高性能ですが、扱い方によっては事故の原因になることがあります。
たとえば、「高温下での放置」「落下による内部損傷」「経年劣化」などは、バッテリーの発熱や膨張、最悪の場合は発火を引き起こすリスクを高めます。
ここで、MOTTERUが特にお伝えしたい安全の基本ポイントを紹介します。
真夏の車内や直射日光の当たる場所、冬の極端な寒冷地に放置しないでください。
高温はセル内部の化学反応を活発化させ、発火の危険性を高めます。また、低温では内部抵抗が上昇し、性能低下やセル損傷の原因になります。
モバイルバッテリーは精密機器です。落としたり、ぶつけたりすると内部構造が破損し、ガス膨張や発煙の要因になります。
もし、膨らみ・焦げ跡・異臭などが確認された場合は、絶対に使用を続けないでください。
ある報告によれば、使用中に落下させた後、すぐに発火に至ったモバイルバッテリーの事例もあります。
引用元 nite.go.jp+1
出力が高いUSB PD(Power Delivery)対応モデルを使用する際は、必ず規格に適合したケーブルを選びましょう。
規格外ケーブルの使用は、過熱や出力エラーを招き、バッテリーだけでなくスマートフォンにも影響を与える可能性があります。
例えば、ネット通販で安価に流通しているケーブルや充電器の中には安全基準を満たしていないものもあります。細部まで安心して使える環境を整えることが重要です。
長期間使っていない場合でも、半年に一度は充放電を行いましょう。リチウムイオン電池は時間とともに自然劣化します。点検を習慣化することで、異常の早期発見と安全維持につながります。
3~4年を目安に、新しい製品への買い替えを検討してください。リチウムイオン電池の寿命は有限であり、経年による化学劣化は避けられません。「まだ使えるから」と使い続けることが、思わぬ事故につながることもあります。
________________________________________
◆ 安全性の証 ― PSEマークについて

日本国内で販売されるモバイルバッテリーは、電気用品安全法に基づく PSEマーク の取得が義務付けられています。PSEマークは「安全基準に適合した電気製品」であることを示すマークであり、信頼性の証です。
MOTTERUのモバイルバッテリーはすべてPSE取得済みで、国内の厳格な安全基準に沿って設計・製造されています。このマークは、ユーザーの皆さまに「安心して使える製品」を届ける私たちの約束でもあります。
________________________________________
◆ 近年の出火・火災件数など具体的数値データ
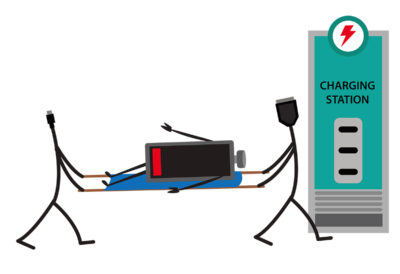
安全性能や対策を語る際、最新の実態データを把握しておくことはとても有益です。ここでは、国内で報じられている「リチウムイオン電池搭載製品」、特にモバイルバッテリーに関わる出火・火災事故の数値を整理します。
• 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(略称 NITE)が公表した資料によると、2020年~2024年の5年間に「リチウムイオン電池搭載製品」の事故通報件数は 1,860件 に上りました。うち約85%にあたる 1,587件 が「火災事故」へと発展しています。
引用元 nite.go.jp+2nite.go.jp+2
• 同資料では、事故発生には季節的な傾向があり、特に「6月~8月」の時期にピークを迎えている点が指摘されています。これは、気温が上昇することでリチウムイオン電池の内部温度も上がりやすく、熱暴走リスクが高まるためと考えられています。
引用元 nite.go.jp+1
• また、東京都の 東京消防庁によると、2024年1月~6月末までに「リチウムイオン電池からの出火(火災)件数」が 107件 に達し、前年同期(79件)を28件上回り、過去最多のペースで増加しているとのことです。製品別では、モバイルバッテリーからの出火が最多だったと報じられています。
引用元テレ朝NEWS+1
• ごみ処理施設でも、リチウムイオン電池搭載製品が原因とみられる火災が全国的に多発しています。例えば、 総務省 の調査によれば、2023年には全国50市のうち45市(約9割)で「リチウムイオン電池が原因とみられる火災」が発生し、19~23年の5年間で処理施設での大規模被害(稼働停止など)が15市で計17件確認されています。
引用元 ITmedia
• さらに、ある地方消防の案内では、令和6年(2024年)には「住宅火災件数」が全国で106件に上ったとの報告もあります(調査方法や範囲に注意が必要ですが、傾向として「増加」が明確です)。
引用元 富士山南東消防本部
• 出火直前の使用状況も、東京消防庁の公表データで整理されています。令和5年(2023年)中の“リチウムイオン電池搭載製品による出火”として、合計167件の事例が集計されており、そのうち「ネット通販で入手したもの」が44件中13件(約29.5%)と、通販経由の製品が割合を占めていることが明示されています。
引用元 東京庁公式辞典
これらの数字は、確定的に「すべてのモバイルバッテリー製品」で起きた事故を網羅しているわけではなく、「報告された事故」「製品評価機構・消防庁などに通報・集計されたデータ」に基づいています。それでも、モバイルバッテリーが搭載するリチウムイオン電池をめぐるリスクが“無視できないレベルで存在している”という事実を示しています。
特に注目すべきなのは、「モバイルバッテリーからの出火が最も多い」という製品別の指摘です。NITE資料では、リチウムイオン電池搭載製品の中で「モバイルバッテリー」が事故件数で最多となっていることが確認できます。
引用元 nite.go.jp+1
また、事故が夏場に集中していることも見逃せません。気温上昇に伴い、車内に放置されたバッテリーが内部温度上昇・膨張・発火に至る例や、電車内・駅・映画館などで使用中に発煙・出火に至った例も報じられています。
引用元テレ朝NEWS+1
これらのデータを踏まえると、モバイルバッテリー・リチウムイオン電池搭載製品を選び・使い・廃棄する際には「安全」を前提にした意識が不可欠であるといえます。
________________________________________
◆ MOTTERUの安全への取り組み

モバイルバッテリーの安全性は、製品設計だけでなく、「製造」「流通」「使用」「廃棄」までの全プロセスで守られるべきものです。MOTTERUはその全体を見据え、安心を“つくる・届ける・守る”ための取り組みを重ねています。
1. 使用済みバッテリーの回収とリサイクル
モバイルバッテリーは一般ごみとして捨てることができません。誤って捨てられたリチウムイオン電池が原因で、リサイクル施設や処分場で火災が発生する事例が全国的に増えています。
引用元 朝日新聞+1
MOTTERUでは、回収・リサイクルの体制を整え、ユーザーにも適切な廃棄方法・回収方法を案内しています。
2. ロット番号による製造管理
MOTTERUでは、各製品にロット番号を付与し、製造情報を一元管理しています。これにより、製造時期や生産ライン、品質検査の記録などを迅速に特定できる体制を整えています。万が一トラブルが発生した際にも、迅速な対応が可能です。
3. 新しい電池技術 ― 準固体電池の採用に向けて
現行のリチウムイオン/リチウムポリマー電池も厳格な品質基準のもとで製造されていますが、さらに高い安全性を目指して、MOTTERUでは「準固体電池」の採用を検討しています。
準固体電池は、従来の液体電解質に比べて揮発性が低く、熱暴走を起こしにくい構造を持っています。発火リスクを大幅に抑えられることから、次世代の安全基準として注目されています。
この新技術を用いたモデルは、今後の製品展開の中で段階的に導入予定です。技術が成熟するまでには時間がかかりますが、「より安全で、より信頼できるモバイルバッテリー」への第一歩だと考えています。
4. 異常検知・温度制御システム
MOTTERUのモバイルバッテリーには、内部温度や出力電圧を監視する安全制御ファームウェアが搭載されています。使用中に異常な温度上昇や過電流が検知された場合、出力を抑制したり充電を停止したりすることで、事故を未然に防ぐ仕組みを設けています。
________________________________________
◆ 情報発信による啓発活動
モバイルバッテリーは、生活のすぐそばにある製品。だからこそ「危険」という認識を持たずに使われることが多く、正しい知識を広めることが、安全を守る第一歩だと私たちは考えています。
MOTTERUでは、公式サイトやSNSなどを活用し、「安全な使い方」「廃棄・回収方法」「買い替えの目安」などを定期的に発信しています。こうした情報発信は、製品そのものの価値を伝えるだけでなく、「安心を共有する文化」をつくる取り組みでもあります。
________________________________________
◆ 「誰もが持ちたくなるプロダクト」を、安全とともに
便利でスタイリッシュなだけでなく、信頼して持てる、安心して使えること。デザイン・使いやすさ・安全性――そのすべてが調和した時、人は自然と「これを持ちたい」と感じます。
MOTTERUはこれからも、ものづくりの原点である「人の暮らし」に寄り添い、安全で信頼できるモバイルバッテリーを通じて、社会全体の安心を支え続けます。
________________________________________
◆ 最後に:少しでも事故を防ぐために
最後になりますが、皆さまに覚えておいてほしいポイントを改めてまとめます。
• 落下・衝撃・ぶつけに対して注意を払うこと
• 規格に適合したケーブル・充電器を使い、過充電・過放電を避けること
• 長期間使っていない場合でも、**定期的に充放電(点検)**すること
• リチウム電池搭載製品を「可燃ごみ/不燃ごみ」に捨てないこと。所定の回収ボックス・自治体指定回収日を守ること
• 製品は3〜4年程度を目安に買い替えを検討すること
• 製品購入時、PSEマークの有無・信頼できるブランド・製造ロット管理の有無を確認すること
• 万一発火・異臭・膨張・焦げ跡などを感じたら、ただちに使用を中止し、安全な場所に移動・専門家へ相談すること
これらを実践することで、大切なデバイスを支えるモバイルバッテリーを“安心して使える道具”として活用できます。
私たちMOTTERUは、今後も安全意識を起点に、デザイン・性能・信頼の三位一体を目指していきます。
どうぞ安心して、そして快適にお使いいただければ幸いです。
MOTTERUのモバイルバッテリーはこちらから
MOTTERUの製品はこちらから










